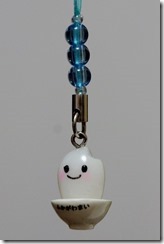『歌・こよみ365完全版』17枚目は仕事のことが多く歌われます。この曲は17枚目の最後にふさわしく、NHK『プロジェクトX』ばりのお話です(『プロジェクトX』ではありませんが「北海道の米」などいくつかの番組がNHKで放送されているようです)。
この記事は「ななつの星に願いを込めて」の後半に、加筆・修正をしました。転載の転載になりますがご容赦ください。
北海道の農協から依頼された、北海道米の歌です。依頼主「米米北海道のブログ」は、勤務先を説得して楽曲を発注されたそうです。
以前に別のところで書いた記事「北海道で米を作ることと、路上から武道館へ行くこと」の後半と「デジタルカメラの技術と農産物の品質管理」を転載します。
北海道米販売拡大委員会では、北海道米のイメージソングを作ってもらい、PRにつとめることになったようです。歌うのは、作詞・作曲も担当した宮崎奈穂子さん。シングルCDとして発売されていますが、ほとんどは北海道内で配布されたそうです。
シングルには3曲入ってます。3曲目は「夢を歌えば」で、これは「歌・こよみ365曲」のテーマ曲ですから実質2曲です。1曲目が以前紹介した「ななつの星に願いを込めて」、2曲目が今回紹介する「日本一の米所を目指す北海道米の歌 Rice Land Hokkaido」です。
どちらの曲も、北海道米に対するネガティブな言葉で始まるのですが、2曲目の方が衝撃的にネガティブでした。
●日本一の米所を目指す北海道米の歌 Rice Land Hokkaido
まず、出だしからすごい。1曲目の冒頭「北海道米なんて」程度じゃ済みません。
「やっかいどう米」と言われた時代があった
「鳥またぎ米」とばかにされたりもしたけれど
「ほっかいどう」じゃなく「やっかいどう」ですよ。鳥も食わずにまたいでいく「鳥またぎ」ですよ。こんな言葉、生産者に対して言えますか。でも言われたのでしょうね。
実は、北海道JAの方に聞くと、当初は1曲目も「やっかいどう米」だったんですが、あまりにひどい言葉なのでやめたそうです。
北海道の多くの米ブランドとともに、専門用語も登場します。たとえば「タンパク仕分け」。米は、タンパク質含有量が少ない方が米の食味が良いそうです。低タンパクな米を選別するのが「タンパク仕分け」のようです。
仕分けされた米はブランドからはずされ加工米となるそうです。自分の作った米が二級品になってしまうのはつらいことでしょう。
歌には「7.4はきっと今年も厳しいけど」という数字も登場しますが、これはタンパク仕分けのしきい値のようです。1年かけて育てた米が、7.4という数字で選別されるわけです。
それにしても、よくこんな生々しい歌ができたなあ、と思います。
楽曲としては1曲目の方がスマートですが、生産者には2曲目の方が心に響くかもしれません。ちょうど宮崎奈穂子さんの「夢に歌えば」と「路上から武道館へ」のような関係でしょうか。
2つの曲は同じシーンを歌っていますが、ずいぶんと印象が変わります。
▲「路上から武道館へ」
▲「夢に歌えば」
それにしても。現在でも、北海道で米作りをすることは大変なことではないかと思います。まして、先人の苦労は並大抵のことではなかったと思いますが、農協のWebサイトにはそうした苦労話が一切登場しないのがかっこいいですね。
これから北海道米を食べようと思いました。
「デジタルカメラの技術と農産物の品質管理」
デジカメの普及で、写真のうまい人が増えました。フィルム時代は撮影→現像→評価のサイクルが長く、評価してもらった頃は撮影時の感覚を忘れてました。今は撮影と同時に自分で確認できますし、各種SNSで瞬時に評価をもらえます。
それに比べて農産物は、多くの場合、年に1回しか評価されず、結果を活かすのは翌年です。それでも品種改良を継続的に続ける努力は尊敬に値します。『日本一の米どころを目指す北海道米の歌 Rice Land Hokkaido』にも「1年1作だから」という歌詞があります。
私の父の実家は滋賀県の米農家で、親戚にも多くの農家がいます。作付けしているのは主に「日本晴」です。
一般に流通している米では分からないと思いますが、米は生産者が違うと違う味になります(米に限らず農産物はだいたいそうです)。父の実家と、叔父の家では味が違います。隣の田んぼでも違うので、土壌の影響は最小限のはずです。やはり作り手の工夫が味に影響するようです。。
農協は、複数の生産者の米を混ぜることで一定の品質を確保しているのだと想像しますが、それでも極端に外れた品質の米があると困るでしょう。歌詞にも、均一性を保つ努力が描かれます。
「北海道米」というブランドを確立するために、米の品質を安定させたい。そういう思いが、宮崎奈穂子さんの歌「日本一の米所を目指す北海道米の歌 Rice Land Hokkaido」から伝わってきます。
農家の方は皆さんこだわりがあり、結構大変だったんじゃないかと思います。7分59秒『歌・こよみ365』最長の曲に、いろいろ考えることがありました。