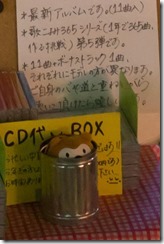部活動や仕事をしていて気付くのは、「人によって得手不得手がある」ということです。学校の勉強の場合は、得手不得手と言っても実際には勉強量の差に過ぎなかったりします。
もちろん、勉強量の差が生じるのは得手不得手があるからですが、そもそも授業内容は個人の資質の差によって変化しないように考えられているから当然です。
しかし、部活動になると、決まった学習手順があるわけではないので個人差が大きくなってきます。社会に出ると、その差はもっと広がります。
ただ、そこで「私は、この仕事苦手だから」と避けていては成長できません。
心理学者のキャロル・ドゥエック氏は、能力観(自分がどれくらいの能力があるかの認識)を「固定的能力観」と「拡張的能力観」に分類しました。
固定的能力観は、自分の能力を固定されたもので、進歩しないものだと考えます。一方、拡張的能力観は、自分の能力は変化するもので、これからも伸びていくと考えます。
ドゥエック氏の著作の邦訳『「やればできる!」の研究―能力を開花させるマインドセットの力』では、それぞれ「こちこちマインド」「しなやかマインド」と表現しています。
「こちこちマインド(固定的能力観)」の人は、「今ある能力」で物事に取り掛かろうとするため、予想外の出来事や難しいことに直面するといった逆境に弱いそうです。
一方「しなやかマインド(拡張的能力観)」の人は、「今の能力ではできないかもしれないけど、とりあえず挑戦してみよう」と思うそうです。
面白いのは、子供をほめるとき「100点取ったね」と言うのはあまり良くないそうです。結果の評価は「現在の自分の能力が素晴らしい」と思ってしまい、能力を固定されたものと考えやすいからです。
そうではなく「頑張った結果が100点という評価になったね」のように、過程(プロセス)をほめると「そのプロセスを繰り返すことで、もっと高い能力が得られる」と思うそうです。
この曲のタイトルは「カタクナ」と「やわらかく」ですし、歌詞にも「『嫌だ!』って言って止まっちゃう」と「とりあえずやってみよう」が対比されています。ドゥエック氏の著書を読んだのでしょうか。
2番では、ものの見方が紹介されます。自分と異なる意見を出されても
「そっか、確かにそういう見方もあるよねえ」って
やわらかく受け止める方が 前に進めること分かってる
さあ、どうしようか
とあります。受け入れることがいいのに決まっているのに「さあ、どうしようか」というのは、次のフレーズで分かります。
カタクナじゃなくて やわらかくありたい
これが実際なかなか難しくて困る でもそうなりたいな
このフレーズのメロディが、ほんとに困っている感じがしてなかなか素敵です。
ところで、宮崎奈穂子さんを紹介するときにはこういう文章がよく使われます。
サポーター(ファンクラブ会員)を1万5,000人集めて、武道館コンサートを実現
今までに売ったCDは5万枚(武道館直後は4万枚と言ってました)
数字による結果は分かりやすい指標なので、よく使うのですが、ファンは1万5,000とか5万という数字は大して気にしていないでしょう。おそらく宮崎奈穂子さん本人もそうだと思います。
1万5,000人集めるのにどれだけの工夫と苦労をしたのか、武道館に人を呼ぶためにどんなことをしたのか、そこが大事なことだと思っているはずです。
宮崎奈穂子さんが以前に所属していた事務所では、期間を区切ってCDの販売目標がよく設定されました。一番有名なのが、彼女の最後の数値目標となった「50日間で5,000枚のシングル」ですが、これは未達でした。
とは言え、最後まで粘る姿に心を打たれた人は多く、私も生まれて初めて同じCDを2枚買ったくらいです(著書に「(CDを)上げる人を思い出したから」と戻ってきた人のことが書かれています。他にも同じような人がいたかも知れませんが、私がそうでした)。
もし「50日間で5,000枚のシングル」が達成していたら、結果だけが評価されてしまったかもしれません。そうしたら、武道館の集客が6,000人(主催者発表)しかなかったことで、自分の限界を感じてしまったかもしれません。
武道館を満席にすると1万5,000(これがサポーター人数の根拠)、音楽イベントだともう少し減るのですが、実際にアリーナ席から後方を見渡すと、2階席に相当な空席がありました。「失敗」と思ってしまっておかしくないくらいです。
もちろんプロですから結果は大事ですが、それがすべてではありません。もし、結果だけで評価していたら、もしかしたら今の宮崎奈穂子さんはなかったかもしれませんね。
似たような話を「「も」(239/365)」でも書きました。あわせて読んでいただけると幸いです。

「やればできる!」の研究―能力を開花させるマインドセットの力